


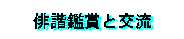
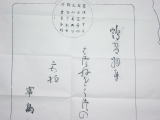 �i�U�j���̑��i���C���C�K���K���j�𗬍L��
�i�U�j���̑��i���C���C�K���K���j�𗬍L��
�@[�����Ɉœ��N����]�̋�ӂɂ��Ă̍l�@
�w�锼�����咟�x�Ɏ��߂�ꂽ����b�l�i�锼���b�l�j�̂��̋�ɂ��āA�F�s�{����������̏��搶���X����u���v�Ƃ́u�|�������؋����v�̎��ł���Ƃ̌������f����ϖʔ����Ǝv���܂����B
�����̏����ɂƂ��āA�u���v�Ŕ������u�|�������̑���v���A���ɐ��Z���邱�Ƃ��N���s���ł���A���ׂ̈�"���K�̂�肭��"�͓��̒ɂ����ł������Ƒz���o���܂��B���̎؋����́u�|���Ƃ�v�ƌ����A������ы����Ăق���"�����炵����"�ł������Ƃ̎��A���̂Ȃ�Α�A���̑����Z�����߂��Ă��܂��A���u�������v���ł������炾�����ł��B�����Ƌ��ʼn��낵���邭�V�N���}�������Ƃ�"�����̐؎��Ȋ�]"�����߂���ł��B���Ƀ��[���A�Ɉ��锭��Ɗ��S�������ւ����܂���B
���̋�́u���v���L�[�|�C���g�ɂȂ��Ă��邱�Ƃ͋^���]�n������܂���B���́u���v�ɂ����"�o�~�̔o�~����ʔ������ۗ������Ă���"�ƍĔF���v���܂����B
����Ɠ����ɁA�锼���b�l�͢�œ���Ƃ������t��Y���鎖�ɂ���Ă��̋���X�Ɂu�V�ѐS�v������"�o�~�̐^����"�ɍ��߂Ă���Ǝv���悤�ɂȂ�܂����B�͂��߂ɂ��̔���ɐڂ������ɂ́A���͂��̢�œ���̈Ӗ����ǂݎ�ꂸ�A�������̌��t����C���[�W�����u�Â��v�����o������ʂ��炢�����v���y�т܂���ł����B�������F�s�{����������̐搶���̉����ǂ�ł��邤���ɁA�̓ǂ��Ƃ̂���{�̒��Ţ�œ���Ɋ֘A����L�q�����������Ƃ��v���o���A�O�̂��߂ɖ{�I�ɖ����Ă������̖{��ǂݕԂ��Ă݂܂����B�����āA��œ���Ɋ֘A���鎖�ׂčs�����ŁA�b�l�̈Ӑ}������悤�ȋC�ɂȂ�܂����B
�u�œ��v�Ɋ֘A���鎖���������ɏЉ�䌟������K���ł��B
����ꁄ �Ɂu�œ��v���×����u���z�i���������j�̓��v�ƌ����Ă����ƌ��������L�鎖�ł��B
�ޗǂ�����ɏo��ŒZ�̃R�[�X�A����R�i�����R�j�z���́u���z�̓��v�ƌĂ�Ă��������ł��B�w���t�W�x�Z���ɁA�����R���z���鎞�̉̂Ƃ��Đ_�Њ����V���C�i���݂����̂��݂�����܂�j�����̂悤�ɉ̂��Ă��܂��B
�� �u���z���̂��̓��ɂ��Ă����Ă���g�̊C�Ɩ��t�����炵���v
�@�u���z���̓��v�ł��鐶��z���̓�����A���z�ɏƂ�P�����̊C�͈�]�ł��A�u�����Ƃ��v�ƌ��������̓�g�̊C�����t����ꂽ�̂ł��낤�c�c�����̘a�̂̈Ӗ��ł��B
�w�Î��L�x�ɂ��Y���邪�u�����i�������j�̒��z���̓����͓��ɍK�s�ł܂����v�Ƃ�������Ă��邻���ł��B���̗l�ɌÑ���u���������̓��v�ƌ����Ă����̂ł��B
�܂��A�{���钷�́u�����̒n���̋`�͕s�ڂł���Ƃ��Ȃ���A�t�߂ɈÓ��i���炪��Ƃ����j�ƌ����n�������邱�Ƃ���Í�i���炳���j�Ƃ����ӂŃN�T�J�ƌ������̂ł͂Ȃ����v�ƌ����������ł��B�ȏ�́w�����`���x�i�J�쌒�꒘�E�W�p�Ёj���̔����ł��B
�u�Ó��v�v�͐���R�̓쑤�ɂ���܂����A���̑�����R�̖k���ɂ���u�N�T�J��v���u���z�i���������j�̓��v�Ƃ���������݂��܂��B��҂��������Ƃ��Ă��u�Ó��v�́u���������̓��ɋ߂��v�ɂȂ�܂��B
�����܂���Ȃ�A�u�œ��v�Ƃ́u���z�i���������j�̓��̓��v�A���́u�����z���߂����v�ƌ������ɂȂ�A���z���́u�����v�́A�@�@��K������Ȃ����Ƃ̈Ӗ��A�A�@���ԓI�ɂ��������̈Ӗ��ɂȂ�܂��B
�@���̂悤�ɍl����ƁA�锼���b�l�̋�ӂ́c�c�u�|�����v�̎؋���藧�Ă͍����Ɂu�����z���̓��v�ł���B�����ĐV�N������ė���ƌ��������ɂȂ�܂��B���m�Ȓ��ɂ��A�n�R�ɚb�������́u�؋��킸�ɐV�N���}����ꂽ�祥�c�v�Ɖ��Ƃ��؎��Ȋ�]�����߂��Ă���v���̂ł��B
����̎����́A���t�W�̉̂�����Ƃ���u���z���̓��v���瑾�z�ɋP����g�̈�]�ł����ƌ������Ƃł��B��g�Ƃ����ΌÑ�̓�g���Ë{���������ꏊ�ł��B�����āu���䂩��q���|�����ĕS���̕n������m��A�ۖ����������v�ƌ����m����́u�P���E���̐����v���L���ł��B
���́u�œ��̐�Ɍ�����i�F���A���邭�L�X�Ƃ�����g�ł���v�ƌ����������ƂĂ��d�v�ȋC���v���܂��B�u�œ��v��ʉ߂��ĕ��i���K�b���ƕω����鎖�́A�������̊X����ʂ����o���҂ł���Ȃ�Ύ�������ɂ������Ȃ��Ǝv���̂ł��B���i�̌��I�ω��́A�łɏے������u�؋��n���v�̈Â��C���[�W����ς����A�u����P����g�v��]�ނ悤�Ȗ��邢�C�����ŐV�N���}����]���_�ɂȂ��Ă���ƍl���܂��B���̗l�ɍl����Ɗ��m��Ƀv���X���ĎЉ�h�I�Ȑ����ᔻ�v�f��������Ă��܂��B
�w�ȁE������̍�i�ɁA���l�̎����ƓV���ו����j������w��g�x�i�Ḯ\��g�~�j������܂��̂ŁA�ϐ����̗w�ȍ�Ƃł���I����e�F�Ɏ����Ă���b�l�͂��́u��g�v�̖]�ށu�����z���̓��v�ɂ������������Ĉӎ��I�Ɂu�œ��v��}�������\�����\���ɍl������Ǝv���܂��B
�ܘ_�A����́A��a�����g�����āu���z���̓��v��ʂ�ꍇ��z�肵���b�ł��B���̋t�R�[�X���l����K�v������Ǝv���܂��B�@�ł́u�œ��v�����a������̖]�Ɖ��肵���ꍇ�͂ǂ��ł��傤�H�����ɂ͂�͂��������i���L�����Ă���̎�������܂��B������O�̎����ł��B
����O���́A�u�œ��v�̂��鐶��R�i�����R�j�ɂ́u�V�֑D�v�i�ʖ��E�V�̒��D�Ƃ������j�ɏ���č~�Ղ����ƌ����`�����i�j�M�n���q���������̑c�j�̓`��������܂��B
�u�V�֑D�ɏ��āA�����i���ق���j���čs���āA���̋����ɂ�č~�肽�܂ӂɎ���āA�́A����Ėځi�ȂÁj���āw���i����݁j���{�i��܂Ɓj�̍��x�Ɠ��Ӂv�Ə�����Ă���悤�ɁA�u����݂v�ƌ�����a�i�`�E��܂Ɓj�̖����̖����҂Ƃ��������`�����̓`��������܂��B
���{���I�̐_���I�̒��ɂ��u�c���y�V���ɕ������ɁA���ɔ��n�L��A�R�l�Ɏ����B���̒��ɖ��V�֑D�ɏ��Ĕ�э~���җL��Ɠ��ւ�B�c�c�V���Ɍ����ɑ���ʂׂ��B�W���Z���i���Ɂj�̒��S���B�̔�э~���҂́A���ӂɁ@�����`�����Ȃ�ށB�v�Ƃ̋L�q���c���Ă���ƌ����Ă��܂��B
�܂�A����R����u�V���Ɍ����v���������ł���u����݂�܂Ƃ̍��v����a���삪��]�ł����ƌ��������킩��܂��B
�ȏ�̂悤�ɓ�g�����a��������Ă��A���̋t�ɑ�a�����g�������낵�Ă��A�������Ɂu�������Ă�����i�v�ɏo����ƂɂȂ�܂��B���̂悤�Ɂu�œ��v�͏��Ɂu�ł�������ւ̓]���_�v�Ƃ��ẴL�[�|�C���g���Ȃ����t�ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ��Ƃ��v���̂ł��B���Â̓]���̃C���[�W�́u�Łv�ƌ������̈ꎚ�ł��\���ɕ\������Ă���̂ł����A�F�X�̌̎��܂��Ă��̋���ӏ܂���ƁA��X�ɔނ̋�ӂ��ʔ����A�[�݂Ɣ��͂𑝂��Ă���悤�Ɋ�����̂ł��B
��l�̎����́A�u�œ��v�������m�Ԃ͍Ō�̗��ʼnr��ł��鎖�ł��B
�d�z���炪�蓻�ɂ�
�� �e�̍��ɂ��炪��̂ڂ�ߋ傩��
�u�œ��v�ʼnr�m�Ԃ̂��̋��锼���b�l���m��Ȃ��Ƃ͍l�����Ȃ����ł��B�܂��A�b�l�̔o�~���ԒB�͏ԕ��o�~�����^���̐��I�Ȗ������ʂ����l���������̂ŁA�u�œ��v�Ƃ������t�����ɂ��������Ŕm�Ԃ̋��z�N�����ƍl��������������R�ł��B���́u�œ��v�ƌ��������͎�X�ɐS�ՂɐG��錾�t�ł������\�����\���l�����܂��B�b�l���g�������d�˂��o�~�t�ł��藷�������܂����B�܂��e�F���K�k��_����A�m�Ԃ����ǂ����������o�~���Ԃł��B�܂��K�k���ҏW�����u���z���v�̂͂��߂̗��͑����W����A��Y�����Ƃ̋L�q������܂��B�r������_���K�k�ƈꏏ�ɗ������ł����A���ɋ_��͖@�t�̎p�ŗ��ɖ������Ă����o�~�t�������ł��B����̂ɋ_��剺�̔o�~�́u�@�t���v�ƌ����Ă����Ƃ̋L�q������܂��B����Ō}����ߋ���r�m�Ԃ̋�́A����痷���������o�~�t�̐S�ɟ��݂鋿�����������ɈႢ�Ȃ��Ǝv���܂��B���ۂɐ������U�́u�ߋ咆�̐ߋ�v�Ƃ������邨�ڏo�x���j���ł��B
���̑�l�̎������l������ƁA���̔b�l����́u�؋��ŋꂵ�ޏ����v����łȂ��u�o�~�t�ȂǗ��ɖ�������Y���l�v����������g���������邢�l���ƂȂ�Ƃ��l�����܂��B
���́u�����Ɉœ��N����v�ƌ������܂̒Z��������L���鐢�E���ǂ̂悤�ɓW�J���Ă������̂��H�c�����E�S�ɋ����܂ܑf���Ɋӏ܂��q���A"�V�ѐS"����̐�̐i�s���Ă��������ł��傤�B�z�����Ă��ƂĂ��y�����A�܂��ْ������`����ĎQ��܂��B
���傩�����Ȃ��c���ōs�����E�A�܂��Ƃ�ł��Ȃ������ɓW�J���čs�����E�c���ꂪ�A��̖ʔ����E��햡�ł���悤�ȋC���v���܂��B
�锼���b�l������q�E�����̎Ⴋ���ɐ������ē`�����ƌ����u�o�~�̎��݁v�Ƃ́A�B�ꖳ��̎��Ȃ̊����ɐ^���ʌ�������������������ł���ƌ����Ă���C���v���܂��B
�ӏ܂Ƒn�삪�����ɐi�s���A�����āu���Ȃ̑Ώۉ��v�������ɘA�O�Ƃ������̒��Ō���Ȃ����ȗZ�����Đ��܂�ς��V�������𐁂����܂�Ă䂭�c�B���̘a���邱�Ƃɂ���ĎY�ݏo����鐢�E�́A���y�̘a���⋤�̂悤�ɐS�n�ǂ��c�����鎞�́A�j���̒��Ŕ�ђ��˗x��c�A���̒��Ŕg�̂悤�ɖ�������c�B�����זE�Ɛl�̂̊W�̂悤�Ɉ��������q���A�S�̂Ƃ��Ă���̗L�@�I�����̂Ƃ��Ă̒��a�����������鐢�E�c�B
�ŋ߁A���́u�̐�̖ʔ����v�������������ł���悤�ȋC���ɂȂ��Ă���܂��B���ăV���[�����A���Y���|�p���u���v���S�����Ă��鑮���E�����T�O�̘g�����������āu���̂̕s�v�c�v�ɔ������悤�Ɂu���R�̋��n�ւ̔��āv�������܂��B����Ȃ��L���鉽���c��������m�I�łȂ����m�I�Ȃ����ł̖������̓����ł��B�A�O��}��Ď�������鎩�݁B�Z�����̊ӏ܂Ƒn��̘A���ƒf��B�`�����d�Ȃ���\���ɐV�N�őS���V�������E�B���ׂĂ��捞�݁A�����a���铌�m�I�ȁu�a�v�����o���Ɠ��Ȍ|�p���E�B�A����y���߂鋫�n�́u����̍S��v���̂āu�Ώۉ����ꂽ�����v�Ƒf���ɐ��ʂ������������u�S�̂�Ƃ�v���K�v�Ǝ��͊�����悤�ɂȂ�܂����B�����Ă��́u��Ƃ�v��u�a�̐S�v���A�t�������Ƃ����Z�����Ԃ��̒��Ŏ������������w�ׂΊw�Ԃقlj���悤�ȋC�ɂȂ��Ă���܂��B����l����Ɩ{���ɉ��[���A�ȒP�ɍl����Ɩ{���ɊȒP�Ȏ��ł����A�ǂ�Ȃɒt�قȗ͗ʂł������ɑf���Ɍ��������Ύ~�߂Ă��炦��u���̑傫���v�����܂��B�������ʂƗD�����ʂ���������s�v�c�Ȑ��E�ł��B�����Ĕm�Ԃ��������u�o�~�T�v�ƌ������t���g���Ă������̈Ӗ����A�O���Ȃ�������������Ă���C���v���܂��B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2002�N�@�@���@
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�t�T