


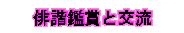
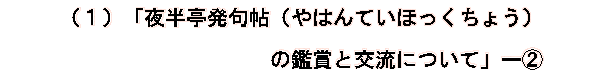
12ー 鳥既に闇り峠年立つや
( Tori sudeni・kuragaritouge・toshi tatsuya/ )
季語は「年立つ」で新年。下五の「や」切りで、一句一章スタイルの流れるような調べを有する格調のある句作りである。現代風の写生重視の鑑賞でいけば、「(あの大晦日の西日を受けて飛んでいった)鳥は、既に、(生駒山の)闇(くらが)り峠を越えて、新しい年の夜明けの空を飛んでいるのであろうか」とでもなるのであろうか。
ところが、どうやらこの「鳥(とり)」は、大晦日の「掛け取り」(借金取りの「とり」)のようなのである(宇都宮大学名誉教授・丸山一彦説)。
即ち、この句の意味は、「大晦日の借金取りの野郎は、今頃、大晦日の真っ暗な暗がり峠を既に越えたのであろうか。そして、もう既に、新しい年になったのであろうか。( そうならば、借金を返さずに,晴れて新年を迎えることが、できるのだが…)」とでもなりそうなのである。こうなると、どうにも、現代に横行する五七五の俳句とやらとは、異質の別世界のような五七五の世界のように思えてくるのである。
しかし、そもそも俳諧(俳句の原初的な姿)とは、このような「言葉の戯れ」の「笑い」と「謎」とを内包するものであったのであろう。そして、この「言葉の戯れ」という典型的な方法として、俳諧の世界には、「謎」句仕立てにする「抜け風」(省略風)という句作りのスタイルが存在していたのである。この謎句の典型的な句の一つとして、巴人の師匠の一人でもある其角(きかく)の句の、
「まんじゅうで人を尋ねよ山ざくら」
がよく例示として上げられる。この「まんじゅう」は「饅頭頭」の坊主のことで、「頭」が抜けとなっているとか、「堂塔の下の土台を饅頭がた」といって、その「がた」が抜けとなっているとかの説が昔から現在に至るまで語り告がれているのである。そして、間違いなく、巴人はこのような句作りを得意とする其角の流れの江戸座の流れの中で活躍した俳人であったということなのであろう。
とすれば、巴人のこの掲出句の上五の「鳥既に」の「鳥」は、「(掛け)とり」の「とり」と解することこそ、巴人の作意に適う鑑賞ということなのかも知れない。
さて、ここまでが、「蕪村研究会」での鑑賞以来、この句の謎解きの全てであろうと思っていたのだが、「蕪村研究会」の良き理解者である一人の女性からの電子メールで、この巴人の句の中七の「闇り峠」は、「直越(ただこえ)の道の峠」という意味が隠されており、「借金をただ(一銭も払わず)で越すことのできる峠」との意味も考えられるのでは、との参考情報を頂いた。この解釈の由来は「万葉集」の巻六の、
「直越え(ただこえ)のこの道にしておしてるや難波の海と名付けけらしも」
にあり、古来から生駒山を越える「直越の道」が大和から河内に出る一番の近道で、その峠に「闇り峠」があるというのである(谷川健一著『白鳥伝説』集英社)。
このことを踏まえて巴人がこの句を作句したとしたら、巴人というのは、そして、それは、当時の俳諧の一線級の宗匠と呼ばれる方々に共通していえることなのであるが、彼らは大変な言葉遣いのマルチニストであったということを思い知るのである。
さてさて、では、こういう謎解きや、こういう、その句の典拠の何かを探るということが、「古句鑑賞」の全てかというと、決してそうではないのである。「何かひかれる」・「何か気にかかる」・「何か魅惑される」という…,これが、古句鑑賞のスタート点であり、そして、このことは、現代俳句鑑賞のスタート点でもあり、そこに何らの差異もないとうことなのである。

3-(1) 「夜半亭宋阿(早野巴人)と夜半亭俳諧の流れ」・・・・上のリンクをクリックして下さい。